MIアイデア発想塾は、生産性を上げる為に、質問力、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン等を知恵ある方法で賢く使い、企業力を強化する組織です。
生産性を上げるとは
洞察力と生産性の総合的な関係説明
当組織では、長期間日本の生産性が低迷している理由は、私たちに欧米の様な知恵がない事が理由と考えています。
その知恵を出す為に必要なる事が、私たちが洞察力を身につける事です。
そこで、洞察力を身につける事と私たちが習慣にしている学びや問題解決法を対比させて、私たちが知恵を出せる様に、洞察力とは何かを説明する事にしました。
〇 私たちの物事の捉え方考え方
私たちの物事の捉え方や考え方では、洞察力を培えない事は、私たちには洞察力がない事で証明できると思います。
私たちは人物事を、表面的変化や違いを見つけ出すように見ています。
意識が、表面的な変化や違いにあり、変化や違いを見分けるような観方をしていて、なぜ、変化や違いが生まれるかは、意識しない観方をしています。
見えているものと見えているものに密接に結びついついた事柄にしか、意識がない見方をしています。
記憶の仕方も、早く正確に知識を引き出せるように、暗記する様に記憶していて、背後にある関係性や構造などに意識を向けて、追求して考える事のない物事の捉え方で記憶しています。
この記憶の仕方と物事の背後の関係性等を考えない事が、記憶している知識に関係性がない独立した知識となり易く、システム思考が苦手な原因になっています。
又人物事の背景を追求する様に考える事が殆どない為、物事の表面だけ見て、背後にある関係性や構造、意図やコンテキストなどは分かりません。
この記憶の仕方をしていると、記憶している知識間に関係性がないだけでなく、物事を動かしている原因等の内情を理解しない捉え方で、表面的に人物事を見る事になります。
その為私たちの記憶仕方は、知っている事の価値はありますが、記憶している知識から、難しい物事を再現したり、新しい物事を生み出したりする様な記憶の仕方にはなっていません。
洞察力は、多くの事を知っている事とは違います。
私たちの知識は、その人が覚えたいと思う事を暗記して、記憶したことを披露するだけでも意味を持つ記憶の仕方をしています。
私たちは、記憶した知識を、並べ替えたり、構造化したり、関係性などを考える事をあまりしません。
持っている知識を、何かの基準で考えて整理する体制化も行いませんので、難しい事ができる為に必要な知識構造にはなっていません。
なぜなら、私たちの知識は、物事を動かしている背後で行われている事を理解していないからです。
しかし洞察力を培う記憶の仕方は、難しい事ができる様な物事を動かしている背後まで記憶する仕方をします。
〇 私たちの物事の記憶のし方ではあまり役に立たない
私たちの知識と洞察力を発揮する為の知識との違いは、物事をどう記憶するかの違いです。
私たちが習慣で行っている言葉で表現できる事をそのまま記憶して知識として行くのと、追求する様に考える事で周辺の事柄と結びつけて知識とするのでは、何かの刺激があったとき、思い起こす事の関連付けが違ってきます。
関連付けて記憶すると、一を聞いて十を知る事ができますが、私たちの記憶の仕方では、一を聞いてわずかしか知る事ができません。
知ることに大きな意味があった時代、例えば、野菜の切り方のような簡単にできる情報が役立った時代には、記憶する事に意味がありました。
現在のように、情報が溢れ簡単に手に入り、社会が高度化複雑化多様化している時代には、知る事で何ができるかが重要になってきて、記憶の仕方が問題になってきています。
しかし、私たちの捉え方は、物事の背後にある関係性や構造などを捉えない記憶の仕方をしています。
この記憶の仕方ではできる様にはならないので、記憶の仕方を変える必要があるのですが、ここで説明することを殆どの人が理解していない為、殆どの人が従来の方法で記憶しています。
〇 私たちの記憶の仕方では、成果が出る様な再現はできない
何かをできるようになるための知識で私たちが知りたいことは、言葉で表現されていない、関係性や意図、コンテキスト等できる様になる為の要素を含んだ物事の背後にある知識と、言葉では表現できない暗黙知的な知識です。
言葉で表せるだけの知識では、原因や本質を始めとした言葉の裏に隠れた関係性や意図等再現する為に重要なものは分からないので、あまり役立つ知識にはなりません。
その為私たちは、具体的な事を説明されないと、できる様にはなりません。
私たちの多くが、表面的に物事を捉え、すぐに引き出せる記憶の仕方をしています。
この記憶の仕方の特徴は、早く対応できる事です。
記憶しているものを、そのまま思い出せば目的が達成できるからです。
私たちの記憶の仕方は、浅く広く知識の量を目標に記憶していているので、何ができるかを考えない記憶の仕方をしています。
それは、知っている事の量や何を知っているかで、その人を評価するシステムが日本にはあるからです。
〇 成果が出せる物事の記憶の仕方とは
知っている事とできる事は別で、できる様になる為の記憶の仕方は、一を聞いて十を知る様な関係性や意図等の周辺知識と結びついた記憶を持っていないと、知っている事からできるようになりません。
なぜなら、できる様にするためには表面的な事だけでなく、物事の背後にある関係性や意図、コンテキストなどを理解していないと、物事をできる様にはならないからです。
私たちが、できるようになりたいと思うものはそう単純なものはなく、言葉では表現されていない原因や本質を含んだ物事の背後にあるものや、暗黙知的なものがある難しい問題だと思います。
できるようになる為の記憶は、言葉で表現されていない実質的に物事を動かしている背後の記憶が必要で、言葉で表せる事を知っているだけでは同じ様に再現できません。
できるように記憶するためには、関連づけで記憶するような、物事を洞察できる力を培う記憶の仕方が必要になります。
〇 私たちの記憶の仕方の特徴と知恵を出す為の記憶の仕方では違うので時系列で見る事もできない
時系列的に物事を見られるのも、関係性や構造などの物事を支えている背景を掴んだ捉え方をしているからで、物事の背後で起きている事から実現性の高い仮説が立てられ先を読む力となったり、過去の経験の洞察から精度の高い今後を予想したりできます。
私たちの記憶は、目に見えない複雑なものでない限り、高度な知識を持っているので、最先端の事にもすぐ気づき、すぐ対応できます。
私たちが、ファッションや流行を取り入れるのが早い事を見ても、お分かりになると思います。
又TV番組を見ても、何を知っているかを問う番組ばかりである事を見ても、私たちが、知る事に興味があって、何をできるかを問わない習慣があるのが、分かるのではないでしょうか。
しかし、この記憶の仕方では、ビジネスの色々な場面で役立つ洞察力は育ちません。
なぜなら、物事を見通す洞察力は、物事の関係性や構造、成り立ちや構成要素などの、物事を支える背景を掴んでいなければ物事を洞察できないからです。
つまり、記憶の仕方が、周辺知識と結びついた記憶の仕方でなければならない、と言う事です。
〇 洞察力を身につける方法に決まりはない
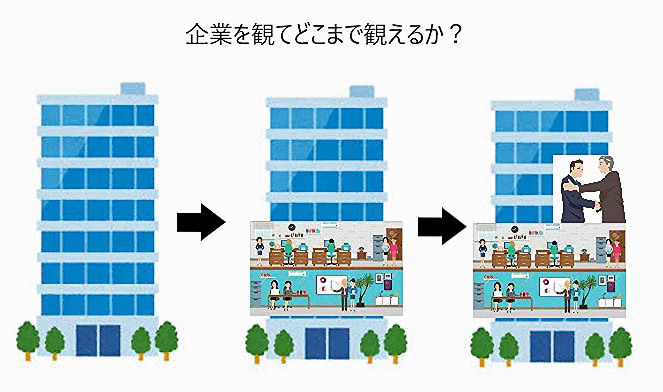
洞察力は、同じ物事を観るにあたり、物事の背後を含めどこまで観えているか分かっているか、この程度を言うもので、決まった観方や物事の理解度がある訳ではありません。
上図で言えば、右に行くほど、洞察できている事になります。
外見しか観えないのか?働いている人まで観えるのか?取引先まで観えるのか?の違いで、相手企業に対する手の打ち方が違ってきます。
観えると書くと、直接見える様に思うかもしれませんが、観えるとは、見えているものからその見えているものの背後まで、ある程度の正確さで分かっている事を言います。
〇 洞察力を身につけるには、人物事を追求する様に考える必要がある
私たちと洞察できる人との違いが生まれる理由は、どこまで観ようとして観ているかで、どこまで企業の内情を探っているかの違いとして生まれてきます。
そう言う理由で、洞察力を培う為には、人物事を追求する様に考える事が必要になります。
しかし私たちは習慣的に、人物事を追求する様に考える事をしません。
そこで、私たちでもできる、物事を追求する様に考える習慣をつける方法を考え出しました。
詳細は、追求する様に考える習慣をつけるには、をご覧ください。
〇 洞察力の定義と、洞察力を身につけると得られるもの
当組織なりに洞察力を定義すると、洞察力とは、一つ一つの物事を、なぜ、どうして?と追求する事により、一つ一つの物事を包括的に解明する事で生まれる、物事を見通す力、と言えます。
洞察力が身につくと、目的に合った要素を多く物事の中から適切に取捨選択できる様になり、知恵を出す基礎として働きます。
洞察力を身につけると、物事を支える関係性や構造、成り立ちや構成要素などが掴めるようになります。
洞察力を身につけると、物事の原因や本質が掴めるので、問題発見や解決が早くできる様になります。
又洞察力を培う過程は一つの物事の解明理解からまた一つの疑問が生まれ、また一つの理解へと、洞察を積み重ねる考え方ができる過程を経る為、洞察できるレベルがどんどん上がって行き、時間が経つと、今まで考えられないような高度の事が考えられたり、できる様になったりします。
洞察力を身につけると、多くの物事から目的に合ったものを取捨選択でき、何が大切で何か必要ないか見分けが付くようになるので、賢い方法で物事を進める事ができます。
私たちの浅く狭い捉え方では、知識を増やす事はできますが、関係性で捉えていないので、知識スキルの積み重ねが殆どできないランダムな知識を記憶する事になります。
知識スキルの積み重ねができるかできないかは、長い間には大きな差となって、ビジネスで行っている事を、洞察できたり、洞察できなかったりするようになります。
洞察力を身につけていると関係性で物事捉えているので、新たなものを取り込む時、仮説を立てて取り込めるので、仮説を検証できるものを見つける事や、仮説では説明しきれない所を補う行動を取れば、新たなものを取り込めるので、物事を取り込むスピードが早くなります。
なぜ、洞察力を培う方法が役立つかと言うと、関係性で常に物事を捉える意識で人物事を見ているので、気づきが多くなる事と、追求する様に考えていれば関係性は多義にわたる事が普通ですから、色々な意識で物事を見られるので、物事を自分に取り込めるスピードが速くなる事です。
洞察力を培えば、賢い事ができる知恵を出せる様になるだけでなく、考える理解できるレベルが上がって行きます。
なぜかは、関係性で人物事を捉えているので、1つの関係性の塊の知識の上に、別の物事を関係性で結びつける事を行いますので、徐々に関係性で理解できる事が広く深くなる捉え方考え方をしているからです。
この方法は、1つひとつの人物事を、原因や本質を通して人物事の理解範囲が広く深くなって行く捉え方考え方だからです。
捉え方考え方のレベルが徐々に上がって行くので、時間が経てば経つほど高度な難しい事ができる様になります。
私たちの様に、1つひとつの知識が独立し易い記憶の仕方では、知識スキルの積み重ね効果が少なく、なかなか高度な難しい事ができる様にはなりません。
ここが洞察力を培う方法でビジネスを進める事の、大きなメリットであり理由です。
〇 洞察力と企業間競争の関係
現在に役立つレベルに達するまで時間は掛かりますが、競争相手より考える事や理解レベルに差がつくので、競争相手に勝てたと言う自信が生まれ、その後は、徐々に競争相手を引き離す事ができる方法です。
自信をどこで得て行くかは、洞察力がつく捉え方考え方に変えて少し時間を掛ければ、気づきや見通せるものが増えるので、その気づき見通しが意識できる様になる事で、自信が生まれと思います。
〇 人物事を洞察できる様にする為には
物事を洞察できる様になる為には、1つひとつの物事の背後にある原因や本質、関係性や構成要素等を詳しく知っている必要があります。
この1つひとつの詳しい物事の理解が、見通せる力、洞察力を生み出し、目的を達成する為の判断や考えの基になって行くので、優れた判断や行動ができる様になる訳です。
特に、私たちにはない、物事の本質や原因を理解した判断ができる様になります。
羽田康祐氏は氏のブログの中で、洞察力とは、目に見えているものを手掛かりに、その奥底にある目に見えない本質を見抜く力と定義しています。
業務を始めとした人物事を洞察できる様にするには、物事の表面的な事だけでなく、物事に含まれている内情(関係性や構造、意図やコンテキスト等)まで理解しないと洞察はできません。
この理解を1つひとつの物事にする事で、表面には表れない共通点や違い、原因や本質等を見つける事ができます。
〇 洞察力が身につくと可能になる事
1つひとつの物事を表面だけでなく内情まで理解しているので、例えば、既存要素の新しい組み合わせを考えだす事ができ、付加価値を生み出すアイデアを出せる様になったり、1つひとつの物事を比較検討する事で、正確に取捨選択ができる様になったりして、優れた判断や行動ができる様になる訳です。
ここまでの説明でお分かりの通り、洞察力を培う事は、私たちが習慣にしている捉え方考え方ではできない事を、できる様にする基になるスキルを得られると言う事です。
生産性を上げる為の基礎が築けるので、今まで出来なかった生産性を上げる事もできる訳です。
洞察力が身につくと、ある目的で1つひとつの人物事をより正確に取捨選択できるので、違いや共通点等を見分け、目的に合っているか否かなどがより適切に判断できる様になるので、難しい事ができる様になるだけでなく、成果の大きい目的を達成する事ができる様になります。
もう少し詳細な事で言うと、私たちの見方捉え方では、物事の背後を理解していないので、何か問題が起きて表面に表れて目に見える様にならないと変化に気づけませ。
洞察力を身につけていれば、表面に表れない微妙な変化だけで気づけます。
なぜなら、原因や本質等背後からその物事を見られるからです。
〇 生産性を上げる行動で必要な、俯瞰視、システム思考、原因や本質等との関係は
洞察力と俯瞰視する関係で言えば、1つひとつの人物事の内情を理解しているので、俯瞰視する目的をより正確に出来、目的達成する成果が大きくなります。
ただ、俯瞰視するには、意識を高い位置において、全体を目的達成のために眺めまわす意識が必要になります。
システム思考の関係で説明すると、物事を洞察するそのものがシステム思考を行っていると言う事です。
物事の内情の理解から、目的に合った物事を取捨選択する事で、目的達成を最適化できるのが洞察力です。
システム思考と同じ目的の行為を、洞察力を身につける行為は行っている訳です。
原因を解明したり、本質をあぶりだしたりする事と洞察力の関係は、洞察力を培う過程である、人物事を追求する様に考える過程で、自然に原因や本質が分かってきます。
又、洞察力がついてくると、1つひとつの物事の内情を理解しているので、より正確に原因を突きとめ、本質を理解できます。
〇 どこまで洞察力が身についたかを、測る方法
どこまで洞察力がついたかは、測る事ができません。
どこまで洞察力がついてきたかを見るのには、短期的には前述した通り、気づきの数やどこまで見通せる様になったか、過去と現在を比較する事です。
長期視点では現在考えられる事、行えることで、どこまで適切な判断ができ、どこまで企業貢献ができたか、を診るとよいのではないでしょうか。
洞察力が培われてくれば、適切な判断ができる様になったり、効率的で効果的な事が考えられたりできる様になります。
〇 洞察力が身につくと、考える事行う事全ての事が賢くなる
これらの説明でお分かりの通り、洞察力を培うと、企業で行う事全てが、適切な判断を基に優れた方法を取れるようになるだけでなく、付加価値を生み出すアイデアも出せる様になるので、生産性も上げる事ができる様になる訳です。
私たちの習慣的な見方捉え方では、洞察力が育たない見方捉え方になってしまうので、生産性を上げる事ができないままでいるのです。
洞察力を身につけるとできる事(まとめ)
人物事を見通せる事で、見通しを通して、人物事をより正確に取捨選択ができる様になるので、適切な判断を通して賢い、知恵ある事ができる様になります。
知識スキルの積み重ねができるので、時間が経てば経つほど、高度なビジネスができる様になります。
又洞察力を培うと、1つひとつの物事を理解できる様になるので、既存要素を良く理解出来ようになり、既存要素の新しい組み合わせである、付加価値を生み出すアイデアが出せる様になります。
付加価値を生み出す様なアイデアは、イノベーショにも繋がる、私たちが最も苦手とする事です。
その他にも、問題発見や解決が早くできる様になる。
物事を理解する事が早くできる様になるので、物事を取り込むスピードが速くなる。
物事の本質を理解した行動が取れる様になる。
やることなす事の成果が大きくなる。
問題を早く気づける様になる。
先を読む力が培われる、等の利点が生まれてきます。
「私たちの学びや問題解決法は、無駄が多く効率が悪い」
私たちは、新たなものを取り込む時、他人が考えた、どんな論理から生まれたのかが分からない知識入手して考えるので、現実には私たちが覚えた事が、知識を入手した人にはできない事が多々あります。
私たち知識を得る方も、知ってしまえば出来ると思い込んでしまいます。
これが、私たちの教え方や研修の仕方が、あまり役立たない学びになってしまう理由です。
当HPのID理論では、この欠点を埋める策を多く論じています。
これを避ける為、企業でコンサルティングを行う場合は、コンサルタントが教えた事を実践させ、実践結果を評価し、間違っている事や足りない事を修正したり行ったりして、結果を出せる様にすると思います。
この間違っている事や足りない事を行う場合、殆どの場合、コンサルタントが教える事をそのまま行う事が多く、本人が間違っている事や足りない事を自ら考え、原因に気づき、解決する方法ではないと思います。
その為、問題解決を自ら考え解決する訳ではないので、コンサルタントがいなくなれば、問題を解決する事ができない場合が多いと思います。
これを証明する事として、問題が起きる度に、新しい知識を入手して解決して行くか、再度コンサルタントに頼むかする事が多いと思います。
私たちは、物事を表面的に捉えているので、変化が表面に出てこないと変化に気づけませんし、変化を全く新しいものとして捉えてしまい、また一から新しい知識を得て、問題解決を図る方法が多いと思います。
世の中は確かに変化していますが、人間の本質は、今でも反射的に危険を避ける行動ができる事からも、そんなに変化する事はありません。
人間の本質がそんなに変わる事が無いのと同様に、物事の本質的なものは、そう大きく変わる事はないと思います。
私たちが変化していると思っている事は、物事の本質から見ると、少し表面的な事が変わっただけで、本質は変わっていない事もあると思います。
人の本質が変わっていないのであれば、打つ手も大きく変える必要はありません。
ちょっと工夫するだけで、問題を解決できる場合もあると思います。
世の中で起きている変化は、最初に変化の兆候が出て、次に兆候に敏感に反応する人が出て、それから徐々に普及する、と言う順序を踏んで変化するのが普通です。
しかし、私たちの捉え方は表面的であるので、1つひとつの変化が全く別な変化の様に捉え易いです。
なぜなら、行っている行動が違えば、私たちの捉え方である表面的には、違う事の様に見えるからです。
その為問題解決する場合、新たな知識を得る事から、1からやり直す方法になってしまい、無駄の多い問題解決法になってしまいます。
物事を追求する様に考える事で得られる原因や本質を理解できる事は、問題に気づくのが早いだけでなく、物事を本質から見られるので、本質的な解決策を考えられるだけでなく、最良の解決策を探せる事です。
1つひとつの問題を、別の問題と捉えてしまうと、なかなか仮説も立てられませんし解決策が、手に入れる知識に影響され、限定的な解決策になってしまいます。
洞察力を培う方法で問題解決を図るメリットは、この様にスキルの積み重ねができるので、高度な事ができる様になるだけでなく、結果的に効率的効果的になる方法だからです。
バナースペース
関連項目
生産性を上げるとは
質問力とは
MIアイデア発想塾
〒400-0853
山梨県甲府市下小河原町
Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp