MIアイデア発想塾は、質問の力を使い、バランス・スコアカード、インストラクショナルデザイン、アクションラーニングを導入し、企業力を強化する組織です。
発想力とは
優れたアイデアを出す為には
「当組織のアイデアの出し方の特徴」
近年、よいアイデアを出す事を求められる機会が増えてきています。
しかし私たちが、よいアイデアを出す事はなかなかできません。
そこで、私たちが今まで出してきたアイデアの質を上げる方法を、説明します。
ここで説明するアイデアは、他人と差別化できる様な、私たちがなかなか考え出せないレベルのアイデアです。
実際に業務やビジネスで成果を生み出せる発想と、私たちが考え出しているアイデアの間には、大きな差があります。
この差を埋めるには、今までのやり方を変える必要があります。
私たちの習慣的なアイデアを出す方法では、今企業で役立つ様なアイデアにはなりませんん。
これから説明するアイデアは、私たちの感覚からすると、少しレベルの高いアイデアになりますが、実際には、御社のレベルと出したいアイデアのレベルを考え、御社のレベルに合わせてスタートし、その差をどう埋めて行くかを考える事で、御社のやる事が決まります。
高いレベルのアイデアは、一朝一夕では出せる様にはなりません。
出したいアイデアレベルで、どんな基礎を作ってアイデアを考えるかが違ってきます。
今までより、よいアイデアを出す為には、それなりの基礎を作り、考える必要があります。
この基礎を重視した方法を取り、アイデアを考えだすのが当組織の特徴です。
なぜなら、基礎がなければ、高いレベルのアイデアは考え出せないからです。
あなたの周りに、優れたアイデアを出す人はいませんか?いるのなら、その人を観察して頂ければ、ここで言っている事が正しい事が分かると思います。
あまり知られていないのですが、アイデア発想力は、鍛えれば誰でも身につくスキルです。
なぜ、他所でできない事が当組織はできるのか?
これは、アイデアを出す事に関して、他所では真似ができない程、当組織が色々な事を理解しているからです。
このHPの他の所を見て頂ければ、当組織が、アイデア発想に関して、深い洞察がある事が、ご理解頂けると思います。
ただ当組織では、どのレベルの社員でも、レベルを合わせる事ができますので、誰でもできる、優れたアイデア出す為の発想法をアドバイスできます。
「アイデアを出せる様にする為の関係図の説明」
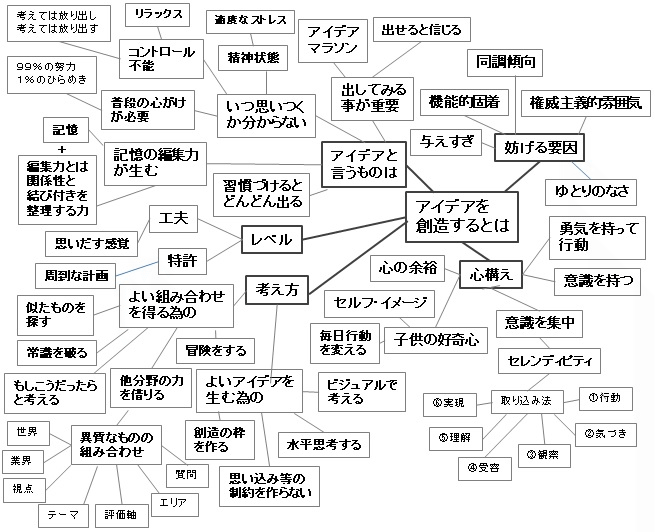
図11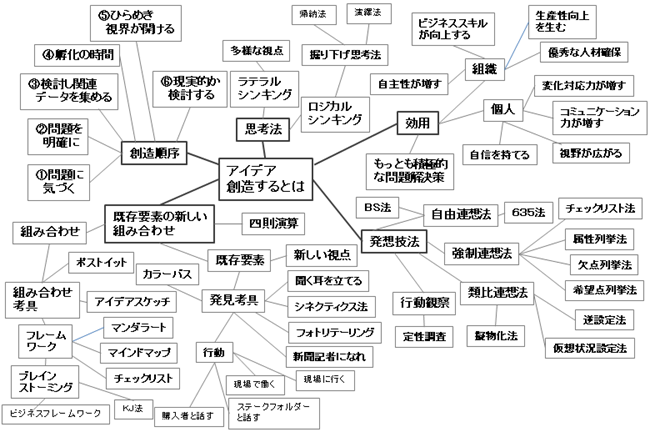
図12
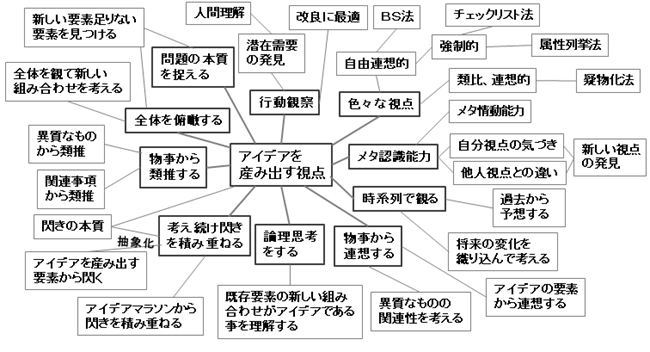
図21
私たちが、役立つアイデアを出したい場合、どんな考え方、心構えで考える必要があるか?を表したマインドマップが図11です。
アイデアを出すとはどう言う事か?これを理解するのに役立てて欲しいアイデアに関する関係図です。
アイデアを出す為の心構えや考え方を持てる様になれば、アイデアを考え出し易くなります。
ここでは、私たちが、アイデアを出す為に開発された発想技法(アナロジーやチェックリスト等図12に少数掲載)だけを使って考えだすアイデアより、よいアイデアの出し方を説明します。
私たちが普段考えだすアイデアより、より多くの人に影響を与える事が出来るアイデアの作り方です。
実際は、発想技法を使ってアイデアを考える事はするのですが、発想技法だけで考えるより、更によいアイデアを出す為には何が必要かを説明して行きます。
私たちが日常業務で考えだす様なアイデアではなく、1つのアイデアで、業務のやり方を変えるぐらい影響力のあるアイデアを出す場合、どう言う考え方や心構えが必要になるかを表したのが図11です。
企業の競争力に関係するほど、高いレベルのアイデアを想定して書いた考え方や心構えです。
図12は、アイデアを出す場合、どんな事をすればよいアイデアが出せるかを表したものです。
情報の集め方やどう言う視点で見ればアイデアを出せるかを、表したものです。
図12以外によいアイデアを出す為に必要になる、アイデア出す為の視点だけまとめた図21を作りました。
よいアイデアを出す為には、色々な視点でアイデアを考える事が役に立ちます。
この視点、見方をまとめたものです。
どう考えようか迷った時等に、使って頂ければ役立つと思います。
私たちの能力は、視点を変えて物事を見ると、全然違うものが見えてくる能力を持っています。
使う、使わないは別にして、知っていれば、必要になった時使えるので、図21に掲載しました。
発想技法1つひとつの説明は、ここでは控えさせていただきます。
ネットで調べれば説明が出てきます。
ここでは、色々な角度から見る事でよいアイデアが出し易い、と言う事だけお伝えしておきます。
「アイデアを出す時に必要になる事」
私たちが、アイデアを出したいと思った時必要になる事を、当組織の見解として説明します。
アイデア出す為に開発された発想法は、現在400程あると言います。
その中で数十種類くらいの数を挙げて掲載したのが図12です。
実際に使うのは、その人によって違いますが3〜5個ぐらいの発想法を使いこなす方が、よいアイデアは出る場合が多いです。
アイデアを出す場合必要になる事は深く考える事です。
私たちが数十種類の発想技法を使いこなす事は不可能に近いので、数種類を使いこなす方が、深く考えられるので良いアイデアが出せる場合が多いと思います。
例えば、オズボーンのチェックリストと、アナロジー思考、希望点列挙法だけを使っても、かなり高度なアイデアは出せます。
アイデアを出す為に必要になる大切な事は、考える事で気づきを多くて、気づきを積み重ねる様に考える事、習慣的な考え方で考えない事、色々な角度(視点)で深く考える様にする事などです。
アイデアを出す為に最初から発想技法だけを使って考えると、発想技法をテクニックとして使う様になり、その場限りのアイデアになってしまう事が多いです。
よいアイデアを考えだす為には、深く考える事が必要になるのです。
「一つ上のアイデアを出す為には」
最初に、高いレベルのアイデアを出す為には、私たちに何が必要になるか、から説明します。
アイデアを出す時に必要になる事は、多視点で見る様な、私たちにはできない事が多いと思うので、徐々に慣らす方法で発想技法等を使いながら、身につけて行く方法を取ります。
なぜなら、私たちの習慣的な物事の考え方捉え方とは、かなり違う方法でアイデアを出す必要があるからです。
アイデアを出す事に慣れる為には、意識して視点を変えて見る事等を、徐々に身につける必要があります。
いきなり発想技法を使い考えるより、できるだけ今までとは違う見方をして、異質なものを組み合わせられる様な考えをし、本質等物事の背後にあるものを良く理解する方法の方が良いアイデアは生まれ易いです。
役立つアイデアは、単なる思いつきでは生まれない程、現在で役立つアイデアは高度化複雑化多様化してきています。
最初に考える癖を作る事が重要になります。
考えなければ、アイデアは絶対に生まれてきません。
この癖をつける事に、物事に疑問を持つ事が役立ちます。
日常行っている事を、疑問視するのです。
疑問視すると、いやでも考える様になります。
この習慣をつける際、追求する様に考える事ができる様に習慣化すると、考えが深く広くなります。
考える事が多くなってくると、色々な気づきが多くなってきます。
この気づきを多くして行けば、いずれはよいアイデアが出せる様になります。
いきなりレベルの高いよいアイデアは出せません。
考える事により、気づきを多くして行く延長線上に、よいアイデアが待っていると思った方がよいです。
気づきを多くする方法でアイデアを出す様にしないと、アイデアが発想技法に影響され、発想技法をテクニックとして使う様になってしまい、その場限りのアイデアしか生み出せません。
一時しのぎのアイデアか、気づきを重ねたアイデアか、この違いの差がが長い間には大きな差になり、私たちが今役だつアイデアか、差別化に繋がる、場合によってはイノベーションに繋がるアイデアになるかならないかの差になって表れてきます。
レベルの高いアイデアは、徐々にしか作る事ができない事を理解し、努力を惜しまないようにする必要があります。
「当組織の方法で出したアイデアは、他所の真似でもなく、他所で真似する事も難しい」
当組織の方法で出したアイデアは、他所の真似になる事はなく、他所が真似できないアイデアになって、御社に大きな見返りをもたらしてくれると思います。
なぜ、当組織のアイデアは真似ではないし、真似もできないかと言うと、1つひとつの気づきは、あなたが考えた末気づいたあなただけの気づきです。
その気づきの積み重ねの末アイデアが生まれるので、あなたの独自性が詰まったアイデアになり、他所の真似にはならないのです。
たまたま似たアイデアが生まれる事はありますが、アイデアを生み出す過程が全く同じとう言う事はあり得ないので、アイデアを実現して行くと、必ず違いが出てくる事になります。
他所で真似もできない理由は、高度化複雑化多様化した現在に通用するアイデアは、気づきを積み重ねて、多くの気づきの上に閃いたアイデアになります。
アイデアを支える多くの気づきは、他所では分かりようもないので、高度で、複雑であればあるほどアイデアを出した人の様には真似できないのです。
少なく見積もっても、先行利益は得られるアイデアになると思います。
私たちは、アマゾンのやり方を真似する事ができない事からも、お分かりになると思います。
私たちが本当に欲しいアイデアは、全く新しい事に気づいたアイデアであったり、他所では真似できないアイデアであったりする訳です。
このアイデアを出す為に必要な事は、気づきを積み上げて行くアイデアである必要があるのです。
発想技法を使い少し考えればすぐ出てくるアイデアでは、真似され易く、よいアイデアにはならないのです。
「どうしたら、私たちがよいアイデアを出せる様になるか?」
どうしたら私たちがよいアイデアを出せる様になるか?この答えがなければ、ここでの説明は無駄になります。
良いアイデアを出す為には、社員自ら考える習慣をつける事から始めます。
日常業務やビジネスで行っている事を疑いの目で見て、疑問に思う事を追求する様に考えて貰うのです。
これを続けていると、業務やビジネスで行っている事を深く考える様になり、やっている事の目的や原因、本質等が徐々に解明され、理解できる様になってきます。
なぜ、日常の業務やビジネスを疑問視して、追求する様に考えると、原因や本質が解明理解できるのか?
これを説明しないと納得いかないと思います。
疑問視する事を習慣化する時、追求する様に考える事を教え、追求する様に考えて貰う訓練を、日常の中で行うのです。
物事を追求する様に考えるとは、どう言う事かは、別ページをご覧ください。
業務やビジネスの目的や原因、本質等が分かってくれば、今まで行ってきた方法を変えるかも知れません。
例えば、業務を追求して考えたら、目的にあった行動をしていない事が分かれば、目的にあった最良の方法を探し、最良の方法に変えると思います。
日常業務でアイデアを出す必要がある場合は、発想技法になれて頂く意味でも、発想技法を使いアイデアを考えて貰う事もします。
その際も、日常の業務やビジネスを疑問視して、分かってきた原因や本質等の知識を使い、アイデアを出して行きます。
考える事を多くする事で、気づきを多くして、業務やビジネスをよく理解し、その理解を基にアイデアを出そう、と言うのが良いアイデアを出す方法です。
現在に通用するよいアイデアを出す為には、業務やビジネスをよく理解しておくことが必要になるのです。
私たちが行っているアイデアの出し方は、先人が考え出した発想技法を使い、アイデアを考える方法が多いと思います。
この方法には限界があります。どんな限界かは、私たちの見方の限界です。
私たちの考え方捉え方は浅く狭い為、現在よいアイデアに必要になる深さや広さがないのです。
業務やビジネスを始めとした人物事の広く深い理解が、よいアイデアを生み出すのです。
業務やビジネスの広く深い理解は、考え方捉え方により生まれるものなので、一朝一夕ではできませんが、一度身につければ、一生使えるスキルとなり、よいアイデアを生み出し続ける事ができます。
よいアイデアを出す為には、私たちの知識主体の問題解決法を、考える事主体の問題解決法に習慣を変える必要があります。
ここをどう乗り切るかが、よいアイデアを出せるか否かの境目になるのです。
多かれ少なかれ、これだけ高度化複雑化多様化してきている世の中では、考えない、知識と真似だけの企業は生き残れないか、安い賃金で働く事になります。
生き残りを図り、利益の出る企業を作る為には、よく考える事が必須になってきているのです。
バナースペース
関連項目
MIアイデア発想塾
〒400-0853
山梨県甲府市下小河原町
Mail tresor@eagle.ocn.ne.jp